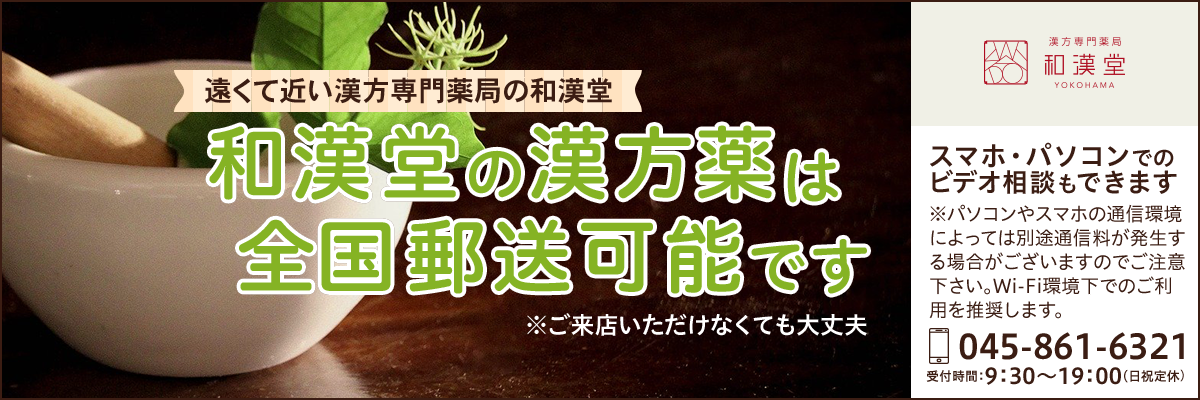2:IBS【過敏性腸症候群】を漢方の視点でみる
よくIBSを下痢、便秘、混合、ガスなど4つに分類します、実は漢方では、この分類はあまり参考にはしません。「下痢タイプです」というとおよその症状が伝わるので便利ではありますが、それによって漢方薬を決めることはしません。
漢方薬では、症状や普段の体調などを聞きながら表・裏、寒・熱、虚・実、陰・陽という独特のものさしを使って体質や病気の度合い、病気の性質などを分析し、それを治療するためにはどの薬がいいかを考えていきます。
ですから下痢タイプのIBSにはA薬、ガスタイプにはB薬という単純な公式はなく、一人ひとり薬が違います。
過敏性腸症候群による急な腹痛・下痢には、セロトニンという神経伝達物質が関わっていることがわかっています。セロトニンが分泌されると腸の動きが活発になるので、食べ物が入ってくる→セロトニン分泌→腸が動く、という仕組みになっているのです。
ところがIBSの患者さんでは消化とは関係なく、ストレスによりセロトニンが過剰に分泌され、運動異常(下痢)や知覚過敏(腹痛)が起こるのです。
西洋医薬ではこの仕組みに着目し、セロトニンの働きを抑えるセロトニン3受容体拮抗薬などが用いられます。
それに対し、漢方薬はセロトニンの存在が知られる前からある薬ですが、昔から”憂いは大腸を傷つける”といい、ストレスと大腸の働きが密接に関係があることを知っていました。
セロトニンの働きを抑え下痢や腹痛を止めることも時に必要ですが、それだとずっと薬を飲み続けなくてはなりません。
もっと根本的なところから治そうとしたら、自律神経を整えてストレスによる異常反応が出ないようにしなくてはなりません。それには、体の調和をとって、結果的に守備力を高める漢方薬が適しているのです。
下痢を止める薬、ガスを止める薬を考えるのではなく、その人の身体のどの歪(ゆがみ)が下痢などの症状をを引き起こすのかを突き止め、歪を治すのが漢方薬です。
漢方は時間がかかるといわれますが、それは根本的なところから治そうとするためです。こうした違いについて、西洋医学は対症療法、東洋医学は根本療法 などといわれます。
IBS【過敏性腸症候群】を克服する
13のヒント